きゅうりは犬に与えてもOK!
| きゅうり | きゅうりには、犬が中毒を起こすような成分は含まれていないため、犬にあげても問題ありません。 |
|---|
犬はきゅうりを食べられる
犬がきゅうりを食べても問題はありません。
愛犬にきゅうりを与える際には、皮の表面のイボを取り、食べやすくカットしてから消化性を高めてあげましょう。
ただし、きゅうりを一度にたくさん食べさせると、水分の取り過ぎによって、下痢を起こすリスクがあります。
きゅうりのぬか漬けやピクルスなどといった人間用の加工品は、犬に食べさせてはいけません。

きゅうりは犬も食べられる
きゅうりは犬が中毒を起こすような成分は含まれていないため、犬に与えることのできる野菜です。
生のままで与えても問題ありませんが、味付けしたきゅうりは与えないようにしてください。
水分をたっぷりと含むきゅうりは、水分補給にも役立ちます。
また、きゅうりは、95%が水分でできているため、低カロリーな食材です。
いつものドッグフードにきゅうりをトッピングしたり、おやつ代わりに小さく切って与えることで、満腹感をサポートすることもできるでしょう。
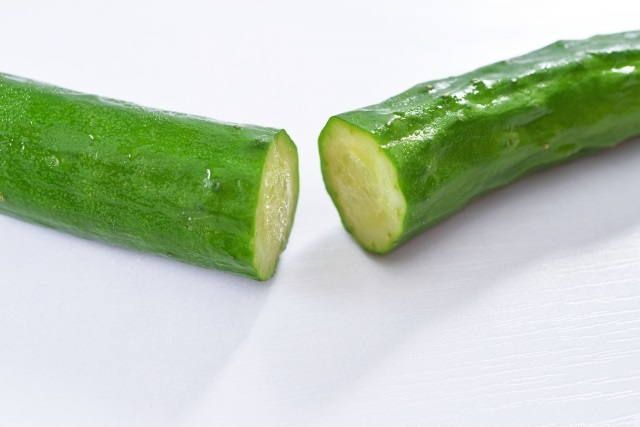
きゅうりのエネルギー量は、100g(約1本)当たりわずか14kcalほど
きゅうりを犬に食べさせる際に注意したいこと
きゅうりは皮は取り除いて細かくカットする
犬は、植物性食物繊維の消化がそれほど得意ではありません。
また、与える際にはみじん切りや細かい角切りにし、食べやすくしてあげましょう。

きゅうりの皮も犬は食べることはできるので、もし食べてしまっても、のどに詰まらせたりしなければ問題はありません。
一日に与えていいきゅうりの量
きゅうりには犬にとって有害な成分や中毒症状のある成分は入っていませんが、どんな食べ物も食べ過ぎることは体調不良につながります。
特に、きゅうりは水分が多いため、食べ過ぎると下痢の原因となりますので注意しましょう。
犬に与えても良いきゅうりの一日当たりの上限は、体重1kgあたりきゅうり10分の1程度が目安です。
犬の大きさごとに分けると。以下の通りになります。
- 体重5kg程度の小型犬……きゅうり1/4本
- 体重15kg程度の中型犬……きゅうり1本
- 体重20kg以上の大型犬……きゅうり1,2本
上記はあくまで目安なので、一日のトータルの食事量やカロリーなどと併せて判断してください。
さらに少ない量から試して、様子をみましょう。

きゅうりの皮も犬は食べることはできるので、もし食べてしまっても、のどに詰まらせたりしなければ問題はありません。
苦味の強いきゅうりには要注意
通常のきゅうりは問題ありませんが、苦味の強いきゅうりには、ククルビタシンという成分が多く含まれています。
ククルビタシンは、きゅうりが動物から身を守るために作り出す物質であり、大量に食べた場合、下痢や腹痛、嘔吐といった症状をもたらします。
栽培の過程で水分不足や寒い気候などの負担がかかると、まれにククルビタシンを多く含んだきゅうりが生産されてしまうことがあります。
愛犬にきゅうりを与える際には、まず飼い主さんが少しだけかじってみて、味を確認しましょう。
いつものきゅうりよりも、異常に苦味を感じる場合には、破棄することをおすすめします。
きゅうりのアレルギーにも注意
犬がきゅうりのアレルギーを持っている可能性もあるので、初めてきゅうりをあげる際には、少量だけを与えて様子を見るようにしましょう。
特に、ブタクサの花粉症を持つ犬は、きゅうりでもアレルギーを起こすことがあるため、与えないほうが無難です。
皮膚や粘膜の赤み・かゆみ、下痢、だるさ、眠気など、犬のアレルギー症状は多岐に渡ります。
もしきゅうりを食べた愛犬に異変が見られた場合、獣医さんに相談しましょう。
きゅうりの加工品はNG
ぬか漬けやピクルス、オイキムチなど、人間用のきゅうりの加工食品をワンちゃんに与えることはやめましょう。
塩や香辛料は基本的に犬の健康に良くないため、人間用に加工された食べ物は与えないようにしてください。
きゅうりを使った手作り食を作る際にも、塩やしょう油、砂糖、スパイス類などの調味料を用いた味付けは一切不要です。

人間用に味付けされた食べ物は、基本的に犬には与えないようにしてください。
きゅうりに含まれる栄養素
きゅうりのほとんどは水分なので、栄養がないと思われていますが、きゅうりにも様々なビタミン・ミネラルが含まれています。
水分が多くさっぱりしているので、夏バテで食欲が低下しているワンちゃんにもおすすめです。
- カリウム
-
カリウムは、細胞のバランスを保つミネラルです。
ナトリウムとセットで働き、塩分の排出や、血圧や心臓を正常に保つ働きがあります。
- ビタミンC
-
ビタミンCには、加齢や運動による酸化ストレスに対して働きかけます。
重要な栄養素ですが、健康な犬猫は体内でビタミンCを生成できます。
- ビタミンK
-
ビタミンKには、骨や血液の流れを正常に保つ働きがあります。
多くの酵素の活動を補助をする成分です。


